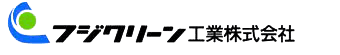|
 私たちの身のまわりは、実にカラフルな世界で形づくられています。それらの色は木や草花、空などの自然が作り出している色と、人によって作られ、彩られている色とがあります。人がモノに色をつけるようになったのは、遠い遠い昔からです。旧石器時代に描かれた洞窟の壁画にも色が使われていたからです。やがて人は、衣服にも色を使うようになりました。 私たちの身のまわりは、実にカラフルな世界で形づくられています。それらの色は木や草花、空などの自然が作り出している色と、人によって作られ、彩られている色とがあります。人がモノに色をつけるようになったのは、遠い遠い昔からです。旧石器時代に描かれた洞窟の壁画にも色が使われていたからです。やがて人は、衣服にも色を使うようになりました。 |
| 水との係わりが深い染料 |
色あざやかな花を見て、その色を服に移し取りたいと考える人がいても不思議ではありません。古代の人々も美しい花や葉を布に直接摺りつけて服を染めていたようです。
ところで、繊維を染めるには、基本的に水の存在が欠かせません。染料は水を媒体として繊維の中へ入り込むことができるからです。一方、一度染まった布は水の中へ入れても染料が容易に溶け出すことはありません。いまでは合成染料の発達により、必ずしも水を必要とはしないものもありますが、染料は水との関係からはじまっているのです。 |
| 薬から生まれた染料 |
中国では本草を中心とした医術が古くから発達していました。そして本草の煎汁の色から染料が生まれ、さらに煎汁を濾すときに使った布が灰汁でさらしてあると、より美しい色になることから媒染剤を知ったといわれています。こうして中国で発達した染料と染色技術が、日本へ伝えられたのは3〜4世紀頃とされています。そして19世紀に合成染料が発明されるまで、染料には天然染料しかなく、染料の原料は同時に漢方の原料でもあったのです。
ところで、これらの植物からはどんな色を染めることができたのでしょう。 |
 |
黄色系のものとして、みかん科の植物の黄檗(きはだ)、黄味をおびた赤い実をつける梔子(くちなし)、多年草の大黄(だいおう)、刈安(かりやす)などがあり、鮮やかな黄色としては鬱金(うこん)があります。刈安は7世紀頃の庶民の服としても使われていました。
赤系統として現在でもよく知られているのが紅花(べにばな)です。エジプト地方の原産とされ、日本へは飛鳥時代に伝えられたようです。紅花は口紅、頬紅、食紅としても使われています。茜(あかね)は赤根とも書き、最も古くから使われている染料の一つです。
紫や青系統としては蘇枋(すおう)、藍(あい)などが知られています。蘇枋はまめ科の灌木で芯材を染色材料にし、紫系の染料をつくります。江戸時代には庶民の使用した紫はこの染料で染めました。このほかにも櫟(くぬぎ)、樫(かし)、椎(しい)といったぶな科の植物、丁子(ちょうじ)、五倍子(ごばいし)(ヌルデ)、矢車附(やしゃぶし)といった植物が使われていました。
それぞれ、樹皮、幹材、葉などを煮出して染液をつくり、そこへ糸や布を浸して染めるのですが、染料が繊維に直接染着しないときは、アルミ、鉄、銅、錫などを使った媒染剤の溶液にひたし、染料が染着しやすくします。これを媒染といいます。この媒染に何を使うかによって、同じ植物でも、異なる色となってきます。 |
|
|